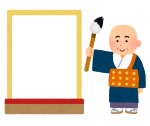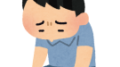「戒名ってなんですか?」
と聞かれたらあなたは何と答えますか?
「え~、死んだ後につける漢字だらけの名前でしょ?仏壇に戒名が書いてあるやつが確かあったよね・・・」
以前の私はこんな程度の認識しかありませんでした。

もし、あなたが戒名についてよくわからないのであれば
戒名とは何ぞや?というところから話しますのでぜひご覧ください。
そして、あなたが大切な方のお葬式を考えているのならば戒名をつけるべきかどうか、という点についても解説しております。
参考にしてみてください。
そもそも戒名とは何か?
戒名とは何か?
そもそもは仏門に入った人に与えられる名前のことです。(これはとても重要な点なので、後で詳しく説明します。)
戒名を授かるということは、仏様が定める戒めや規律を守りますよ、という宣言でもあります。
ではどのように戒名はつけられているのか?ということですが、
その構成要素はざっくりと4つにわけることができます。
具体的には「院号」「道号」「戒名」「位号」の4つです。
1つずつみていきましょう。
「院号」とは?
院号とは何か?
それは、自分でお寺を建てるほどに寺院に貢献した人、あるいは相当な地位や功績のあった人に与えられる称号です。
最近では格付けの意味でつけられることが多いです。
〇〇院が一般的ですが、それ以外に、〇〇庵や〇〇亭などがあります。
「道号」とは?
「道号」も、一種の格付けとしてつけられます。
自分の趣味・特技・性格などを反映した言葉の字をあてます。
「戒名」とは?
続いて「戒名」。本来の戒名とはこの部分の名前です。
故人に関係のある文字を使うため、名前の一字をとることが多いです。
「位号」とは?
最後に「位号」ですが、その名の通り、仏教徒としての位を表します。
性別、年齢、地位の高さによって名前が違ってきます。
成人男性であれば、信士・居士・大居士、
成人女性であれば、信女・大姉・清大姉などがつけられます。
ちなみにこの順にランクが上がっていきます。
その他子供の場合や宗派によって様々な名称があります。

有名人の戒名の例
では実際にどのような名前になるのか?
昭和の歌姫である美空ひばりさんの戒名を例に取りますと、
「茲唱院美空日和清大姉」
・・・パッと見ただけだと読めないですね。
「じしょういん びくう にちわ せいだいし」
と読むそうです。
(美空は「びくう」より「みそら」と呼んだ方がいい気がしますが・・・)
茲唱院・・・院号
美空・・・道号
日和・・・戒名(美空ひばりさんの本名は加藤和枝さんです)
清大姉・・・位号
となります。
清大姉は成人女性では最高位です。
戒名のつけ方、分かりましたか?
ちなみに、先ほど院号や道号は格付けの意味でつけられている、と言いましたが、江戸時代以降になると、有力な大名たちが院号を好んでつけるようになったそうです。
早い話が、お金で院号を買ったということです。
現在も戒名のランクによって戒名料が高額になるのはその名残です。
戒名は必要なのか?
ここで重要なことは、戒名とは「仏門に入った人に与えられる」ということです。
つまり、他の宗教を信仰、あるいはそもそも無宗教な方にとっては必要のないものなんです。
「死者には戒名をつけなければならない」、というのはハッキリ言って思い込みです。
しかも、本来は仏弟子になった証につけるもの、つまり生前につけるべきものです。
ですが、私たち一般人は仏弟子にならずに亡くなりますよね。
なので「仕方なく」死後につけるようになったのです。
戒名の本来の意味を考えていくと、はたして戒名が必要かどうか悩みませんか?
最近では仏教以外の宗教を信仰する人も増えてきました。
私の家の近所のスーパーにも、よくイスラム教徒と思われる方がいらっしゃいます。
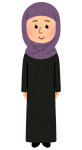
それに、そもそも「私は無宗教です」という方も多いですよね。
そこで、ここからは戒名をつける必要性のある場合とない場合について考えていきます。
戒名をつける必要がある場合とは?
ズバリ、菩提寺がある場合ですね。
戒名がない場合、納骨を拒否されるトラブルもあります。
あるいは菩提寺があるのに違うお寺から戒名をつけてもらった場合も、納骨を拒否されたり、新しく戒名をつけ直しされて倍の戒名料を払うハメになった・・・
なんてこともあるんです。
せっかくお葬式を安くしよう、と言っているのにこんなことで費用が高くなってしまっては馬鹿らしいですよね。
なので、菩提寺があるかどうかはちゃんと調べておきましょう。

他にも、菩提寺があるわけではないけど周りの親族が戒名をつけるよう勧めてくることも考えられます。
あなたが戒名は必要ないと思うなら、話し合ってみることをおススメします。
その上で、どうしても戒名を付けなければいけないという状況になった場合、あるいはあなた自身が、「戒名はつけておいた方がよい」という考えでしたら戒名はつけましょう。
そうは言っても、戒名料は抑えたい!「安く戒名をつける方法はないか?」というニーズが高まってきたこともあり、最近では戒名授与を低価格で行う業者があります。
その一つに「お坊さん便」があります。お坊さん便を使うと、定額・低額でお坊さんの手配や戒名授与が可能になります。
戒名をつける必要がない場合とは?
それは「戒名をつける必要がある場合」以外、ですね・・・当たり前ですが。
私自身は戒名をつける必要はないと考えています。
今後仏門に入るつもりもありませんし、お寺にも何にも貢献していないのに、戒名だけつけてもらうというのは変な話だと思うからです。

最近では、私のように考える人が増えてきました。
それに何より、戒名料だって馬鹿になりません。
院号や道号が格付けのためにつけているように、他の宗派を信仰する人や無宗教の人には、戒名それ自体が一種の格付けになってしまっているのです。
その格付けのために高額なお金を払わなければいけない・・・
だったら戒名っていらないよね、となるのは自然な考えですよね。
まとめ
というわけで、私は特に理由なく戒名をつけることには反対です。
「つけないと不安だから」
という理由で戒名をつけるとして、そのために決して安くないお金を払う必要があるのか?
とは言っても
「戒名つけないと不安だ」
「罰が当たりそう」
という気持ちになるのは分かります。
そんな方のために、先ほども紹介しましたが、お坊さん便のように定額で戒名をつけてもらえるサービスがあります。気になる方は、チェックしてみてください。
自分ではよく分からない、という方は葬儀社の担当者に相談してみてください。

しっかりした葬儀社なら、戒名についても親身になって相談に乗ってくれるはずです。
やはりお葬式のことは、お葬式のプロに聞くのが1番です。
とはいえ、葬儀社は正しく選ばないとトラブルの元です。自分に合う葬儀社を選びたい!どうやったら良いんだ!?とお悩みの方は、

を参考にしてみてください。