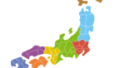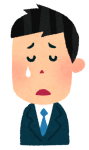
亡くなった後、すぐにしないといけない手続きってあるの?
大切な方が亡くなったあとには、お葬式の準備の他にもたくさんの事務手続きが必要になってきます。
いざという時にあわてないように、事前に必要な書類について確認しておきましょう。
死亡診断書(死体検案書)の手配

必須の書類です
これがないと火葬などその後の手続きができませんから、とても重要な書類です。
病院などで亡くなったときに、臨終に立ち会ったり死亡を確認したお医者さんが「死亡診断書」を交付してくれます。
ちなみに、不慮の事故などで亡くなった場合は、監察医から「死体検案書」を交付してもらいます。
いずれも数枚必要になりますので、コピーは多めに取っておきましょう。
葬儀社の担当者に確認しておくとよいですね。
死亡届の提出

死亡診断書(死体検案書)を手配したら、市区町村役場に死亡届を提出します。
届け出できるのは、次の市区町村役場です。
①故人の亡くなった住所
②故人の本籍地
③届け出る方の所在地
死亡届を提出できるのは親族、同居人、家主、地主、後見人(葬儀社の担当者も含む)です。
亡くなってから7日以内に提出しなければなりません。(海外で亡くなった場合は3ヶ月以内)
費用はかかりません。
死亡届の提出は、次に解説する「火葬許可申請書」と同時におこないます。
火葬許可申請書

死亡届と同じタイミングで提出します
先ほどの死亡届と一緒に提出します。
死亡届と同じく亡くなってから7日以内に行います。
火葬の日程調整で注意すべき点は2つ。
①火葬は、原則死後24時間経たないとできない
②「友引」は、多くの火葬場が休みになっている
役場に提出すると「火葬許可証」がもらえるので、火葬の当日に火葬場へ持っていきます。
なお役場によっては、この時点で火葬料金を支払うことがあります。
火葬後には「埋葬許可証」をもらいましょう。
※多くの葬儀社は、死亡届と火葬許可証の手配をやってくれるので、実際に自分でこうした手続きをやる必要がないこともあります。
世帯主の変更届
世帯主が亡くなって14日以内に「世帯主変更届(住民異動届)」を提出します。
世帯主が亡くなって残された世帯の構成員が2人以上の場合、かつ配偶者以外の方が世帯主になる場合に提出します。
ただし、世帯主である夫が亡くなって妻が世帯主になる場合などの「次の世帯主が明らかな場合」には、この届けの提出は必要ありません。
ちなみに、15歳以上であれば世帯主になれます。
そのため、残された家族の中に15歳以上の子供がいた場合は「世帯主変更届」の提出が必要です。
手続きはどこでするの?
手続きは、故人が住んでいた市区町村役場で行います。
届け出るのは新しい世帯主・同じ世帯の構成員・代理人です。
必要な書類は「国民健康保険証(加入している場合)」、免許証などの本人確認書類、印鑑、「委任状(代理人の場合)」となっています。
保険証の返却

亡くなった翌日から健康保険の資格を失うので、保険証の返却を行います。
ちなみに、このときに一緒に葬祭費の請求も行っておくと便利です。

国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入していた場合
自営業などで国民健康保険に加入していたときは「国民健康保険資格喪失届」を、75歳以上(65歳~74歳の障害者も含む)だった場合は「後期高齢者医療資格喪失届」をそれぞれ提出します。
亡くなってから14日以内に手続きを行います。
手続きは故人の住んでいた市区町村役場で行います。
さきほど紹介した届は窓口でもらえるので記入して提出します。その際に必要な書類は以下の通りです。
| 返却する書類 | 国民健康保険の被保険者証(世帯主が亡くなった場合は世帯全員分) |
| 国民健康保険の高齢受給者証(対象者のみ) | |
| 後期高齢者医療の被保険者証(対象者のみ) | |
| 必要な書類 | 戸籍謄本(死亡が記録されたもの) |
| 世帯主の印鑑(認印OK) | |
| 届出人の本人確認書類(運転免許証など) | |
| 後期高齢者医療対象者のみ必要 | 相続人の印鑑 |
| 相続人の預金通帳(高額医療費がある場合) | |
| 限度額適用認定証 | |
| 標準負担額減額認定証 | |
| 特定疾病療養受療証 |
厚生年金保険など、国民健康保険以外に加入していた場合

故人が会社員だった場合は、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格喪失届を年金事務所に提出します。
これらの手続きについては、会社側で行われることが一般的です。その場合、健康保険証も会社に返却すれば問題ありません。亡くなってから5日以内に手続きが行われます。
退職手続きについて

会社員が亡くなった場合、死亡日の翌日を退職日とします。
必要な手続きは、
①健康保険証の返却(被扶養者のものも含む)
②会社から貸与されていたもの(社員証、制服など)の返却
③未払い給与、退職金、自社持ち株、社内預金などの精算
④死亡退職届の提出
⑤その他会社の求める書類(遺族厚生年金の手続きを会社が代行する場合など)の提出
※被扶養者の保険加入について
亡くなった方の扶養に入っていた方は、死亡日翌日から保険資格を失います。
ですので、亡くなった方の保険証と一緒に自分の保険証も返却しなければなりません。
そのあとの手続きとしては、2通りあります。
①自分自身が国民健康保険や国民年金に加入する
②同じ世帯に会社員がいれば、その方の扶養に入る手続きを行う
まとめ
ここまで、亡くなってからすぐにしないといけない手続きについてまとめました。
お葬式以外にもかなりバタバタします。
こうした手続きについては、葬儀社に事前に確認をとっておき、分からなければすぐに尋ねられるようにしておいてください。
そういえば、お葬式が終わったのになんでこんなに忙しいのか・・・と父がぼやいておりました。
葬儀社に事前に相談していたので、ある程度忙しくなるというのは分かっていたつもりでしたが、それでもかなり大変でした。
ちなみに葬儀社によっては、こうした一連の手続きもサポートしてもらえます。
何事も事前の準備が大切です。
いざ亡くなってからバタバタ慌てるよりも、きちんと準備して「何をしたらいいのか?」を知ってからお葬式やその後の手続きを行うことを強くオススメします。