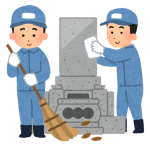実家の墓が遠方なので、お墓参りや管理が大変・・・
子供にも迷惑かけたくないし・・・

夫婦それぞれの家のお墓、今後どうしよう・・・

墓を継いでくれる人がいない・・・
私も年を取って、墓参りにもいくのが大変だし・・・
こうしたお墓に関する悩みを持つ人は少なくありません。
私自身も、父方の墓の管理についてどうしようかと悩んでいる状態です。
このまま何もしないでいると、無縁仏になってしまうかもしれない・・・それはあまりにも哀しいですから。
そこで近年、「墓じまい」「改葬」という言葉がよく聞かれるようになりました。
「墓じまい」とは今ある墓を撤去すること。
一方「改葬」は、新たな場所に遺骨を納めることをいいます。
最近では、納骨するのではなく「散骨」を選択する方も増えていますね。(散骨については、後日別記事でまとめる予定です)
この記事では、墓じまい・改葬について考えている方に向けて
・墓じまい・改葬とは何をするべきなのか?その手順は?
・墓じまい・改葬の費用はいくらかかるの?
・墓じまい・改葬のメリット・デメリットとは?
こうした事柄をまとめていきます。
※墓じまいと改葬をまとめて「墓じまい」と表現しているところもあるのでわかりにくいですが、この記事ではそれぞれ別に分けて考えます。
墓じまい・改葬が増えているワケとは?
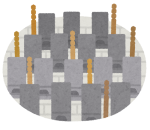
そもそも「墓じまい」「改葬」のニーズがここまで高まってきた理由は、冒頭で書いたような悩みを持つ人が増えてきたからです。
もともとあるお墓から遠く離れた場所に住んでいると、お墓の維持管理が大変です。
だったら地元に残った親族に任せっきりでいいのか?というとそんな単純な話ではありません。
特に高齢になると、定期的にお墓参りするのは体力的にも負担が大きくなります。
私の父方の墓も、少しヘンピなところにあるので、なかなか行きづらいんですよね。
何より「地元に残った私だけ大変な思いをしている・・・」と、親族間のトラブルになりかねません。
さらに、私たちのように長男・長女同士が夫婦になると、それぞれの家の墓の管理まで考えないといけません。
ますます話がややこしくなります。
ちなみに私たちの場合だと、関西と九州にお墓があります。
しかもそれぞれがアクセスの不便な場所にあるので、このまま私たちが墓守を継ぐとしんどいなぁ、というのが正直な感想です。
ましてや、私たちの子供に継がせるのはかわいそうだとも思うんです。
こうした悩みを持っている人が増えている、というのが墓じまいや改葬が全国的に増えている理由です。
まとめますと、墓じまいや改葬が増えている理由は次の通りです。
・遠方にあるお墓の維持管理が大変(夫婦だと両家の墓まで考える必要がある)
・墓守の継承者がいない(あるいは継がせたくない)
・高齢化によって、墓守の負担が大きくなる
墓じまい・改葬の手順について

墓じまい・改葬の手順はざっくりと以下の通りです。
①遺骨の改葬先を決めておく
②親族からの了承を得る
③墓地管理者の了承を得る
④石材店の選定
⑤行政手続きを行う
⑥墓石の撤去・墓地を更地にする
⑦新しい改葬先に納骨する
詳しく見ていきます。
①最初に改葬場所について考えておきましょう。

墓じまいや改葬をしようと思ったときに、まず考えるべきは「改葬場所はどうしようか?」ということです。
いくつか選択肢があります。
合祀・合葬による永代供養
多くの方が、合祀または合葬による永代供養を選んでいます。
合祀墓とは、「骨壺から遺骨を取り出し、他の方の遺骨と一緒に納骨するお墓」のこと。
合葬墓とは、「骨壺のまま、共同スペースに納骨するお墓」のこと。
ただし、合葬は一定期間がすぎると、骨壺から遺骨を取り出して合祀されるケースが多いです。
合祀・合葬による永代供養のメリット・デメリットを簡単にまとめました。
| メリット | デメリット |
| ・費用が安い
・管理や供養を墓地の管理者に任せられる ・継承者を考えなくてよい |
・一度合祀した遺骨は取り出せない
・個人的に法要などができない ・「他人の遺骨と一緒になる」ことへの抵抗 |
永代供養の大きなメリットは、費用の安さです。
最初に払う費用の中に永代管理料などが含まれているため、以降はお金がいらないというケースが多いですね。
共有の参拝スペースが設けられているので、「お墓参り」も可能です。
納骨堂

納骨堂は寺院などが管理する、共同の遺骨収蔵スペースのことです。
多くは屋内に作られます。
| メリット | デメリット |
| ・管理や供養を任せられる
・天候を気にせず参拝できる |
・一定期間後は合祀されることが多い
・お供え物・預けられる遺骨数に制限アリ |
意外と大きいメリットが「天候を気にせず参拝できる」ということでしょうか。
雨の日や暑い夏の日などに墓参りするのは、意外と大変です。
あと、屋外の霊園って意外と高低差があるので、足腰が弱ってくるとかなり体力的にもしんどいんですよね。
納骨堂ではそういったデメリットがない、というのがメリットになります。
手元供養

お墓や納骨堂ではなく、自宅に遺骨を保管する方法です。
最近では「ミニ仏壇」のほか、遺骨の一部をアクセサリーにする方もいらっしゃいます。
一見すると、遺骨とは分からないくらいです。
手元供養のメリット・デメリットはこちら。
| メリット | デメリット |
| ・管理費が一切いらない
・故人を身近に感じられる ・特に事務手続きなく、低価格で可能 |
・遺骨をアクセサリーにすることに対する抵抗
・分骨した残りの遺骨をどうするか決める必要あり |
ミニ仏壇は数万円~から作れますし、特に役所に行って事務手続きが必要・・・なんてこともありません。
ただ遺骨の一部をアクセサリーなどにした場合、残りの遺骨の引越し先を考えなければなりません。
一部をアクセサリーに、残りを納骨堂に収める場合だと、別途納骨堂に対する費用がかかります。
ちなみに、分骨した骨を別の場所へ納骨するときは、分骨証明書が必要になります。
散骨
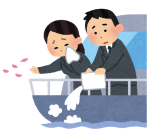
散骨とは、遺骨を細かく砕いて海や山などに撒くことです。
石原裕次郎さんなど、著名な方が散骨されています。
「自然に還る」ということができる、散骨後の管理などの問題を考えなくてよい、という点から人気を集めています。
| メリット | デメリット |
| ・「自然に還る」ことができる
・散骨後に費用や管理が一切不要 |
・すべての遺骨を散骨した場合、「心の拠り所」を喪う
・散骨に対する抵抗 ・散骨場所に注意 |
遺骨を全部散骨にしてしまうと、「どのように故人を偲べばよいか分からない」という意見もあります。
また場所によっては散骨を禁止している市町村もあるので、散骨場所はきちんと調べる必要があります。
②親族からの了承を得る
ある意味、一番大変なのがこの項目。

お墓を潰す!?
なんて罰当たりなこと!!
とにかく、親族一同がすんなり賛成してくれるケースは少ないと考えておいてよいでしょう。
親族の説得に疲れてしまい、墓じまいを諦めてしまったという人も少なくありません。
ですが、墓じまいを考えるということは、必ず理由があるはず。
・お墓の維持管理が辛い
・墓守の跡継ぎがいない
などの理由から、このまま放っておいては無縁仏になってしまう・・・お墓の今後を真剣に考えたからこその墓じまい、ここは粘り強く交渉するしかありません。
自分で勝手に墓じまいを進めてしまって事後報告、というのが最悪です。
面倒ではありますが、きちんと周りの了解を得るようにしてください。
もちろん、交渉の中で「墓じまいをしなくても維持管理の負担が軽減できる」ような結論が出たなら、それはハッピーですよね。
墓じまいの必要はありませんから。
※故人が一定の地位にあった場合
故人が一定の地位にあった場合は、例えば地域の代表者や会社の関係者にも了承を得ておくと良いでしょう。
あとから「勝手にお墓を壊されてしまった」とトラブルにならないよう、配慮が必要です。
③墓地管理者に了解を得る

お墓の管理者である寺院や霊園にも、墓じまいする旨を伝えます。
今後必要になる場合があるので、「埋葬証明書」の発行も依頼しておきましょう。
お寺の檀家の場合、墓じまいする理由を尋ねられたり離檀料を請求される場合があります。
④石材店の選定

墓石の撤去などを依頼する石材店を決めておきます。
霊園や寺院指定の石材店があれば、基本的にはそこを利用することになります。
とくに石材店が指定されていなければ、相見積もりをとるなど工夫すると、かなり費用を抑えられます。
⑤行政手続きを行う

墓地のある自治体の役所で「改葬許可申請書」を発行してもらいます。
これは、遺骨の取り出しと新たな納骨の際に必要になります。
また、自治体によっては現在の墓地の「埋葬証明書」提出を求められますので、あらかじめ準備しておきます。
⑥墓石の撤去・墓地を更地にする

いよいよ墓じまいです。
閉眼供養を行ってもらったあとに、石材店に墓石の撤去・および墓地を更地にしてもらいます。
この墓じまいの費用は、墓地の広さなどで変わってきます。
⑦新しい改葬先に納骨する

お墓や納骨堂など、新しい改葬先に納骨します。
墓じまい・改葬の費用はいくらかかるのか?
ざっと墓じまい及び改葬の手順について見てきました。
ここで気になるのが、「いくらかかるのか?」ということですね。
まず墓じまいそのものの費用でいうと、1㎡あたり10万円ほどが相場といわれています。
ほかにも閉眼供養の際のお布施、離檀料なども含めると30万円~50万円程度でしょうか。
改葬については、新たなお墓を建てるとなると墓石購入などで100万円単位のお金が必要になります。
それ以外の方法なら、数万円からでも可能です。
ただ、依頼するところによって本当に値段はピンキリです。
事前にしっかりと準備しておくようにしましょう。
まとめ
この記事では、簡単に墓じまいと改葬についてまとめております。
ここで紹介した墓じまい・改葬の手順の一つ一つの項目も注意すべきポイントがあります。
詳細は、関連記事を随時まとめていきますので参考にしてみてください。