こんな疑問や悩みにお答えします。
この記事では、以下の点についてまとめています。
そもそも偲ぶ会ってどんなもの?
著名人がよくやっているイメージ?

偲ぶ会について、聞いたことあるよという方もいらっしゃると思います。
よく芸能人の方が亡くなった後に「お別れの会」を開いた、とニュースになることがありますよね。
この「お別れの会」をイメージしてもらうと分かりやすいです。
最近だと、津川雅彦さんと朝丘雪路さんの合同葬や「ちびまる子ちゃん」の作者、さくらももこさんを偲ぶ会などが有名ですね。
お葬式との違いは?
先ほど挙げた偲ぶ会の例でもそうですが、偲ぶ会を開く前に「親族で葬儀を済ませた後」という枕詞がつきます。
つまり、お葬式を終えた後に偲ぶ会を行います。
なので、偲ぶ会の会場に棺があるわけではなく、あったとしてもそこに遺体はありません。
お葬式は、遺体から魂を分離させる儀式を行った後、遺体を処理(日本ではほとんど火葬)しますね。
ちなみにこの「遺体から魂を分離させる儀式」を省略したのが「直葬」とよばれるものです。
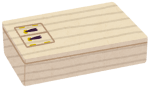
この直葬のように、従来のカタチにこだわらない形式のお葬式も増えてきていますが、メインの目的は変わりません。
そして、最近では家族葬など親しい身内のみで行うことが多くなっています。
一方、偲ぶ会は故人とのお別れももちろんですが、故人の思い出を振り返ることに主眼がおかれています。
そして、その形式は自由です。
遺族が参加するしないも自由ですし、身内ではない人が発起人となって開催しても良いのです。
お葬式に参列できなかった方(故人や遺族の意思で参列できなかった方)が、改めて故人を偲ぶために開く、ということが多いです。
有名人の場合はこれに当てはまりますね。ちなみに、社葬もこの偲ぶ会に含まれます。
要するに、偲ぶ会とは「お葬式とは別に、改めて故人を偲ぶためのイベントであり、形式は自由なもの」といえます。
さくらももこさんの偲ぶ会では、サザンオールスターズの桑田佳祐さんがちびまる子ちゃんのテーマソングを歌っていた、という報道もありましたね。
逆に自由なのだから、お坊さんに読経してもらうなど、告別式のようなことをしてもかまわないわけです。
偲ぶ会のメリット
先ほど、偲ぶ会の形式は自由と書きましたが、これが大きなメリットになります。
「お葬式」ではないから、明るい雰囲気でもOK

もちろん、ニュースでインタビューされていた芸能人の方の中には、涙を流しておられた方もいらっしゃいましたが、偲ぶ会の式次第そのものはとても明るいものでした。
もちろん、泣いてはいけない・笑ってはいけないといったことも決まっていないことが多いです。
自由と言っても、イメージしづらいと思うので、いくつか例を挙げましょう。
偲ぶ会の事例①
都会のおしゃれなカフェレストランを貸し切って、同級生や担任の先生など、故人とゆかりある人たちが食事をしながら思い出を語り合う。
出席者の青春時代に流行した曲をBGMに、店内に飾られた思い出の品とともに故人を偲ぶ・・・
偲ぶ会の事例②
故人は少年野球の監督だった。
祭壇は野球グラウンド風のデザインにし、「プレーボール!!」の掛け声の後、遺族の始球式。
献花や焼香ではなく、「献球」でお別れのあいさつ。
中にはユニフォーム姿で出席する人も。
最後まで故人らしさで溢れた会になった・・・
偲ぶ会の事例③
坂本龍馬没後150年、激動の時代を生き抜いた故人を偲ぶ会が開催された。
勝海舟、桂小五郎など、出席者には歴史の偉人たちが名を連ねる。
お酒を愛した故人を偲び、献花の代わりに献酒。
妻のおりょうさんが好んで弾いた月琴の調べが響く。
料理は、故人の好きだった鯖など土佐のうまいものがずらり・・・
偲ぶ会は本当に自由!!だからこそ問われる企画力
先ほどの例にもありますが、本当に自由ですよね。
はっきり言って、やりたいことをやれます。
ただし、それによって一つ問題が出てきます。
「企画力」がないと、グダグダになってしまう可能性がある、ということです。
企画力と綿密な打ち合わせが必要
「故人は少年野球の監督をやっていた」というキーワードで、きちんと最初から最後まで出席者が飽きることなく、しかもちゃんと故人を偲ぶという目的が達成できるような会を開きたい・・・
そう思ったら、かなりしっかりと企画構成がしっかりしていないといけません。
発起人との打ち合わせも細かくしておかないと、グダグダになってしまいます。
発起人の方が細かくきちんとコンセプトを伝えられるなら、それでもいいと思いますが、現実的には厳しいでしょう。
「野球監督」「熱血オヤジ」など、故人のイメージを何となく言葉にはできても、実際にそれをどう生かすのか?
これって素人にはなかなかできません。
葬儀社にもノウハウがない場合があります
偲ぶ会は増えてきたとはいえ、まだまだ少数派です。
ということは、葬儀社にしてみても、こうした従来のお葬式とは違う形のイベントを担当したことのある会社もまだまだ少ないでしょう。
そんな葬儀社に偲ぶ会を依頼したら、どうなるのでしょう?
たとえば別記事でも紹介した、東京葬儀のような会社であればまだしも、これまでそうした企画をやったことのない葬儀社だと、ノウハウもありませんからなかなかうまくいかないことも多いです。(東京葬儀について詳しくは下記記事を参照してください)
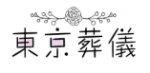
ではどうしたらいいのか?
「実績のある会社に依頼する」
これが正解だと思います。
実績ある会社に依頼するのが一番です
これまで、実際に偲ぶ会や「自由葬」と呼ばれるお葬式をしたことのある会社であれば、あなたの希望にかなった偲ぶ会ができるはずです。
あなたの地元にそうした葬儀社があればいいですが、残念ながらそうとも限りません。
この「Story」は鎌倉新書が運営しています。
私がお葬式を行う際に見積り依頼をした「いい葬儀」の運営会社でもあります。

日本で初めて偲ぶ会をプロデュースした会社(東証一部上場企業)ということで、その実績と経験はバツグンです。
偲ぶ会は「何かしたいけど、何をしたらいいかわからない」という方がほとんどです。
そういった方は「Story」で無料相談が可能です。
何となくのイメージを伝えるだけで構いません。
打ち合わせをしていく中で、形ができあがっていくものです。
偲ぶ会に興味があれば、お気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
偲ぶ会のマナー(平服って?香典は必要?など・・・)
形式は自由だからこそ、困るのが服装などのマナーに関することですよね。
これについてまとめていきます。
「平服でお越しください」とは?
偲ぶ会の案内状が届いたけど、「平服でお越しください」ってどういう意味なんだろう?
と思ったことのある方もいるでしょう。
案内状を見る限り、リラックスした明るく和やかな雰囲気だから、カジュアルな明るめのスーツでも着ていこうかな・・・は危険です。
平服って「普段着」という意味がありますから、勘違いしてしまいそうになるのですが、偲ぶ会においてはNGです。
偲ぶ会での平服のイメージとしては、卒業式に出席する親御さんの服装、という感じでしょうか。
ですので、案内状に特に記載がない限り、基本的には略礼服やそれに準じた服装が適当でしょう。
そして服装選びで忘れてはならないポイントは、偲ぶ会はあくまで「弔事」であるということです。
これを念頭に、男女別の服装についてまとめます。
※後でも解説しますが、偲ぶ会は一般のホテル等でも開かれる場合があります。
そうした他の利用客にも配慮したうえで、喪服や礼服を避けることがあります。
ここでは一般的な服装のマナーについて書きますが、気になる方は主催者(発起人)に確認するとよいでしょう。
男性の場合

男性の場合はダークスーツです。
シャツは柄のないものにしましょう。
靴下は黒、靴は金具や光沢のない黒がよいでしょう。
パーティーではありませんから、ネクタイはきちんとつけましょう。
お葬式ではないので黒でなくても構いませんが、ダークグレーなど落ち着いた色を選びます。
柄なしが無難ですが、目立たない程度なら問題なしです。
※ネクタイについて、黒はお葬式を連想させるので、避けるべきと考える方もいらっしゃいます。
なので無難なのは黒以外の暗色です。
ベルトのバックルや腕時計は光沢のないものに。
ヘビ、ワニなどの爬虫類系の皮は避けましょう。
| スーツ | 黒もしくは暗色 |
| シャツ | 白色、柄のないもの |
| ネクタイ | ダークグレー、ダークブルーなどの暗色又は黒。柄なし、あるいは目立たないもの |
| 靴下 | 黒 |
| 靴 | 黒、金属光沢のないひも靴タイプ |
| ベルト | 黒やそれに準じる暗色。バックルなどに金属が使われていないもの |
| 腕時計 | 光沢のないもの、目立たないもの |
女性の場合

女性は、黒やダークグレーなどの地味でシンプルなスーツやワンピース、アンサンブルにしましょう。
肌の露出は好ましくありませんので、最低でも五分袖くらいのものが無難です。
ストッキングは黒とし、柄物やラメの入っているものは避けましょう。
靴は、黒または暗色でつま先の出ないものにします。(サンダルやミュールは避けましょう)
男性同様、爬虫類系の皮モノではなく、光沢のないものにしてください。
バッグも同じ考えで選びましょう。
コートを着用する場合も、毛皮ではなく、地味な色やデザインが良いです。
メイクも派手にならないよう、チークやアイシャドウなどは出来るだけ抑えます。
口紅は薄い色もしくはリップクリームを塗ります。
香水、ネイルはつけないほうが良いですが、ネイルについては透明あるいは地味な色合いなら良いです。
髪が長い場合はまとめます。
その際は黒いリボンや濃い色のヘアアクセサリーにすると良いです。
髪色については、「明るいと思われるならヘアカラースプレーなどで黒にするべき」という意見もあります。
が、よほど奇抜でない限り、そこまでする必要はないと思われます。
| スーツ | シンプルなスーツ、ワンピース、アンサンブル。色は黒やダークグレーなどの暗色。肌の露出は控えめに(五分袖以上あると無難) |
| ストッキング | 黒。柄物やラメの入ったものは避ける。 |
| 靴 | つま先の出ない、黒または暗色のもの。光沢のないもの。 |
| バッグ | 目立たない色のもの。光沢のないもの。 |
| コート | 目立たない色のもの。毛皮はNG |
| メイク | チークやアイシャドウは控えめ。口紅は薄い色もしくはリップクリーム。ネイルはつけない、もしくは透明なもの。香水は避ける。 |
| 髪 | 長い場合は黒または目立たないヘアアクセサリーでまとめる。 |
アクセサリーについて

基本的には目立たず、控えめにします。
ネックレスは一連のパールにします。
二連以上は「不幸が重なる」につながるので避けます。
ちなみに一粒パールのネックレスは避けましょう。
光ものであるチェーンが使われているからです。
パールの色は白、グレー、黒ですが、白が一般的です。
珠も大きすぎないよう10mm以下(7~8mm程度を勧めるところも)にしましょう。
コサージュをつける場合は、落ち着いた色合いで、目立たないデザインのものにします。
なお、パール以外にもブラックオニキスもOKです。
偲ぶ会の費用(香典は必要?会費はいくら?)
香典は必要か?
偲ぶ会は、何らかの事情でお葬式に参列できなかった方が多く出席されます。
偲ぶ会の発起人が遺族の場合、あるいはそうでなくても遺族が出席する場合、香典は必要なのでしょうか?
答えは、「案内状に指定がなければ持参しましょう」となります。
ただし、最近は会費制にするケースが増えています。
私としても、偲ぶ会をするなら会費制をオススメします。
香典となると、どうしてもお葬式のイメージがありますし、適正な金額が分かりにくいということもあります。
ちなみに、偲ぶ会での香典は1~2万円程度が相場と言われています。
ここら辺もお葬式の相場と少し違うのでややこしいですね。(お葬式における一般的な香典の金額については、下記記事を参照してください。)

会費制のメリット
偲ぶ会の会費制は、出席者だけでなく、主催者側にもメリットがあります。
まず、出席者の立場からしたら特に悩まずに済むということ。
先ほども述べましたが、お葬式における香典と偲ぶ会における「香典」とは、金額が少し異なります。
なので金額の指示がないと、少し不安になりますよね。
ですが、会費○○円と記載されていたら、そうした迷いがありません。
一方、主催者側としても、香典の場合、集められる金額の正確な見積もりができません。
会費制度にすれば、打ち合わせの際にも金額の見積もりがしやすいので、持ち出す金額が分かりやすいですよね。
偲ぶ会の会場
偲ぶ会をどこで開くか?ですが、これは本当に様々です。
前に偲ぶ会の例をいくつか書きましたが、まさに自由です。
自宅、セレモニーホール、レストラン、ホテル、葬儀場などなど・・・
主催者がどのようなコンセプトで偲ぶ会を開くのかによっても違ってきますね。
人気なのは、駅に近いホテルの宴会場などです。
出席者としても利便性が高いのはありがたいですね。
同窓会や一回忌などの区切りのタイミングで開かれることもよくあります。
偲ぶ会の式次第
これもまた、本当に様々ですが、あくまで一例を示します。
①開会の挨拶
②故人の紹介
③黙祷(献花・焼香など)
④献杯・会食
⑤閉会の挨拶
⑥解散(写真撮影など)
まとめ
偲ぶ会は、その名の通り「故人を偲ぶ」ために開催されますが、その形式は様々です。
ですので、マナーなどどうすればいいのか分からないことも多いかと思います。
主催する側も、出席する側もきちんと確認することが大切です。



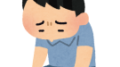
コメント
[…] […]
[…] […]